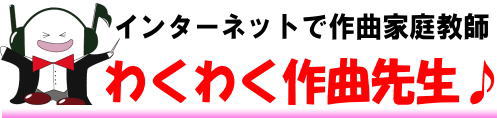今回は「ミキシングのコツ」について書いてみます。
作曲ができるようになると、「もう少し音を整えたい」と感じる瞬間が訪れると思います。
そんなときに役立つのが「ミキシング」です。
ミキシングするためには、昔は高価な機材が必要でしたが、
今はDTMを使って、誰でもミキシングできるようになりました。
今回は、DTMを使ったミキシングのコツや、上達するための練習方法を紹介します。
ミキシングとは?初心者にもわかる基本の考え方
ミキシングとは、各パート(歌や楽器)のバランスをとり、
聞きやすい曲に仕上げる作業のことです。
曲は、ボーカル・ギター・ベース・ドラムなど、
いくつもの音が重なって成り立っています。
これらの音量・定位・エフェクトを調整することで、
曲全体がまとまり、聞きやすくなります。
聴きやすいミキシングとは?“良いミキシング”の基準を知ろう
「良いミキシング」とは、すべての音がバランスよく聞こえたうえで、
なおかつ、主役の音がしっかり伝わる状態を指します。
たとえば、歌モノの曲であれば、
使われている楽器の音がバランスよく聞こえたうえで、
なおかつ、ヴォーカルが歌う「メロディと歌詞」がしっかり聞こえる状態です。
市販の曲を聴くと、一聴しただけでスッと耳に入ってきますよね。
その裏には、音量・定位・エフェクトの調整という計算されたバランスがあります。
まずは、「一番聴かせたいパートが前に出ているか」
それだけを意識するだけでも、仕上がりが良くなります。
ミキシングの基本①:音量バランスを整える
まず大切なのは音量の調整です。
主役が最もよく聞こえるのが大切ですが、他のパートもしっかり聞こえる音量にしましょう。
音量バランスは、土台となるパートから調整していくと
バランスが取りやすいです。
例えば、
ドラム → ベース → コード楽器 → メロディ
という順ですね。
「全部の音をハッキリ聴かせよう」と、全パートの音量を上げると、
かえって聴きづらくなることが多いです。
主役と脇役の差をつけることが、聞きやすいミックスの第一歩です。
ミキシングの基本②:定位(パン)で音の位置を決める
定位とは、各パートが左右どの位置から聞こえるか。
つまり“音の配置”のことです。
映画用の5.1ch用などではない限り、通常は左右のスピーカーやヘッドホンから音を聞くと思います。
パン(PAN)を調整して、ステレオ空間(左右の空間)にそれぞれの音を配置します。
たとえば、
- ボーカル、ベース、バスドラム、スネア → 真ん中
- ギター → 左
- ピアノ → 右
- ブラスやシンセ → 中央寄りの左右
このように少しずつ散らばせると、音が広がって立体感が生まれます。
結果として、自然で聞きやすい空間に仕上がります。
ミキシングの基本③:エフェクトで空間を作る
音量と定位を整えたら、いよいよエフェクトです。
エフェクトを上手に使いこなせるかどうかで、
曲の完成度は大きく変わります。
最も重要なエフェクトを3つ上げるとすれば、
「EQ、コンプレッサー、リバーブ」でしょう。
EQ(イコライザー)
EQは、周波数ごとの音量を調整するエフェクトです。
不要な帯域をカットしたり、強調したい帯域を少し持ち上げることで音を整理します。
特に、ベースとバスドラムは低音域でぶつかりやすいので、
EQで周波数帯域を分けましょう。
こうすることで、お互いが聞きやすくなります。
コンプレッサー
コンプレッサーは、音を圧縮するエフェクトです。
音圧を上げたいときや、ドラムやベースに迫力を出したいときに効果的です。
応用として、音量のバラツキを抑えたり、アタック感を強調したり、余韻を強くすることもできます。
ただし、かけすぎると音が潰れて平坦になるので、
「軽くまとまったかな?」程度から始めるのがコツです。
リバーブ
リバーブは、この3つのエフェクトの中では、
最もなじみがあるのではないでしょうか?
カラオケのマイクや、風呂場を思い浮かべてもらえると分かりやすいと思います。
残響音を作るエフェクトですね。
リバーブは、ボーカルには必須です。
他の楽器にも使いますね。
- 低音楽器 → 少なめ
- 高音楽器 → やや多め
これを目安にかけてみましょう。
ただし、あまりかけすぎると、
音がぼやけてしまうので注意しましょう。
ミキシングでよくある失敗例と対処法
初心者がよくやってしまうのが、
「全部の音をハッキリ聴かせよう」として、
結果的に音が飽和してしまうことです。
また、次のようなミスもよくあります。
- リバーブをかけすぎて全体が濁る
- 低音が重なってモコモコする
- コンプレッサーのかけすぎで奥行きや抑揚がなくなる
こうした失敗を防ぐコツは、“引き算の発想”です。
聞かせたい音を際立たせるために、
他の音をあえて少し引く勇気を持ちましょう。
ちなみに、耳が疲れた状態では判断を誤りやすいです。
時々休憩して、耳の感覚をリセットする習慣をつけましょう。
ミキシング上達のための練習法と耳を育てるコツ
ミキシングは、作曲や編曲以上に経験がモノを言います。
場数をこなすほど上達します。
ですが、ただ数をこなすだけでは上達は難しいです。
おすすめの練習方法は、ミキシングの基本を理解したうえで、
あなたが目指したいジャンルや曲調の参考になる市販曲を聴いて、
音量バランスや空間の作り方を比べてみる方法です。
目標になる曲と比べてみることで、
「このパートは少し音量を落としたほうが良いかも」
「ボーカルのリバーブはかけすぎかも」
のような気付きがありますからね。
まとめ:少しの意識でミックスは劇的に変わる
ミキシングは、慣れるまでは難しく感じるかもしれません。
ですが、次の3つを意識するだけで劇的に上達します。
✅ 主役を決めて音量と定位を整える
✅ 必要な音だけを残す「引き算」で考える
✅ 基本を理解したうえで、参考になる曲と比べる練習をする
最初はシンプルな曲から始めましょう。
ミキシングをしっかりやると、同じ曲でも驚くほど聴きやすくなります。
ぜひ今日から、あなたの曲でも試してみてくださいね(^◇^)ノ
→オンライン作曲講座「わくわく作曲先生♪」トップページへ戻る
→音楽制作の知識大全「音楽レシピ(作り方)の図書館」のもくじへ戻る