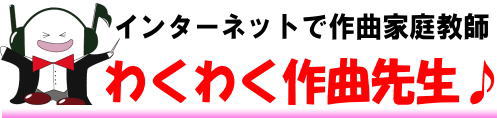今回は「詞先で作曲する時の注意点」について書いてみます。
字から想像できると思いますが、
「詞先(しせん)」とは、まず歌詞を作り、その歌詞にメロディを付けていく作曲方法。
一方「曲先(きょくせん)」とは、まず曲を作り、その曲に歌詞を付けて行く作曲方法です。
現代の音楽制作では、約9割の曲が「曲先」で作られているようです。
とは言え、「この詞に曲をつけてほしい」と頼まれることもありますよね。
僕もクライアントから、自由に書いた詞を渡されて、
曲をつけてほしいと依頼されることがあります。
詞先での作曲のメリットとデメリット
まず、詞先での作曲の大きなメリットは、
何といっても「言葉の力を全面に出せる」ことです。
歌詞から出発するため、作品全体がメッセージ性を帯びやすく、
リスナーに「物語を聞いている」ような印象を与えることができます。
特にラブソングやバラードなど、聴き手に共感してもらいたい曲では、
詞先はとても効果的です。
詞の世界観をそのまま音楽に変換できるので、
聴いた瞬間に、情景や感情が浮かぶ曲になりやすいです。
一方で、デメリットも少なくありません。
歌詞の語数や、言葉のリズムに縛られてしまうため、
メロディを自由に作りにくくなってしまいます。
例えば「あなたに出会えてよかった」というフレーズをそのまま使おうとすると、
語数が合わず、どうしても無理やり詰め込んだメロディになってしまうことがあります。
結果的に「歌いにくい」「メロディがぎこちない」といった印象を与えてしまうことがあります。
さらに、もう一つの大きなデメリットは、作詞者の技術です。
「曲の構成を考えて詞を書ける作詞者」でなければ、
作曲のときに、大きな調整が必要になる場面が出てきます。
作詞者が、ポエムのように自由に言葉を並べただけだと、
曲の小節数にうまくハマらず、
そのままでは曲に乗せられないことが多いんです。
つまり詞先は、作詞者が作曲のことを、ある程度分かっている必要があり、
作詞者の力量にも依存する作り方とも言えます。
あなたが作詞と作曲の両方をするならばいいのですが、
別の人の場合は、お互いが歩み寄らないと、
作品としてうまくまとまらない場合があります。
詞先での作曲のやり方(初心者向けステップガイド)
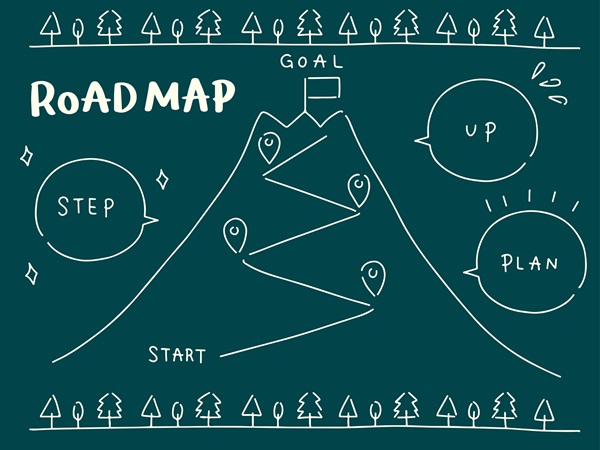
初心者の方も試しやすい方法としては、以下のような手順になります。
- 短い詞を用意する
最初から長編は大変です。「ありがとう」「君に会いたい」など短いフレーズでOK。 - リズムに区切る
声に出して自然な切れ目を探し、拍を割り当てましょう(例:「ア・リ・ガ・トウ」で4拍)。 - メロディを仮置き
鍵盤やDTMで単音を「ド・ド・ド・ド」と置き、言葉を当ててみます。まずは歌いやすさ最優先。 - コードを付けて雰囲気を固める
慣れてきたらコードを付けてみましょう。
まずはI→V→VI→IVなど、定番のコード進行で雰囲気を作るのもおすすめです。 - コードとメロディが合っていないところを微調整
最後に、コードとメロディが合っていないところは、音程かコードを変更して微調整しましょう。
以上の手順で、少しずつ曲の形にしていきましょう。
■よくある失敗例と解決法
よくある失敗のひとつは、歌詞の語数が多すぎて収まりきらないパターンです。
例えば8音で作りたいのに、語数が12語あると、
メロディは窮屈になってしまいます。
改善策は、「同じ意味の短い言葉」に置き換えたり、
助詞を削ったりすることです。
「の」「に」「を」などは意外と省略しても意味が通じるので、
曲に合わせるために削ってしまうのもアリです。
逆に、語数が少なすぎてスカスカになってしまうこともあります。
この場合は、「同じ意味の長い言葉」に置き換えたり、
同じフレーズを繰り返したり、
「Wow」「Ah」「Yeah」といった言葉を足して補うと、自然に聞こえるようになります。
ただし、いつも歌詞を直せるわけではありません。
作詞者の意図を尊重しなければならない場面も多いでしょう。
そのときは、メロディ側を柔軟に調整します。
例えば「ありがとう」という詞を3音に収めたい場合、
「アリ、ガ、トー」のように、1音に複数後を詰め込むように作ります。
逆に、8語に収めたい場合は
「アーリ、ガー、トーー」のように、1音を伸ばすように作ります。
こうした調整の工夫を覚えておくと、
詞先での作曲がしやすくなります。
プロの作詞家と作曲家のやり取り
詞先の作曲では、作詞者と作曲者のコミュニケーションがとても重要です。
実際、僕が経験したケースでも、渡された歌詞のままでは
「どうしても曲構成がおかしくなる」、
「詰め込み(または間延びした)メロディで不自然になってしまう」、
ということがよくありました。
そんな時に勝手に直してしまうと、トラブルの原因になります。
作詞者にも、その詞に込めた想いがありますからね。
これを解決するには「相談」のスタンスが欠かせません。
例えば「ここの歌詞を、このように変えても良いですか?」と確認を取るようにしましょう。
もし、相手が相談しにくい人だとしても、
「この部分を少し短くすると、もっとメロディが活きると思います」
「ここを繰り返すとサビっぽさが出ますよ」など、
提案型の言い方を心がけると角が立ちません。
作詞者の表現を尊重しながら、作曲者の立場で、
作曲的な視点を加えるように提案するということですね。
詞先での作曲をする機会があれば、
以上の注意点を意識して、作曲してみてくださいね(^◇^)ノ
→オンライン作曲講座「わくわく作曲先生♪」トップページへ戻る
→音楽制作の知識大全「音楽レシピ(作り方)の図書館」のもくじへ戻る