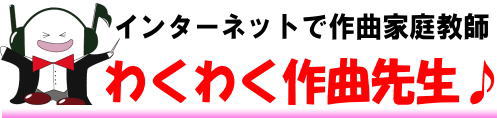今回は「拍子」について書いてみます。
4/4拍子や3/4拍子、6/8拍子といったおなじみのものから、ちょっと難しそうな変拍子、
そして、それぞれの拍子の特徴や、さらに作曲にどう活かすかまで、
分かりやすく紹介します♪
拍子の基本ルール
まずは「拍子」の基本について簡単に説明しておきます。
拍子は分数で書かれますが、これは分母と分子に意味があります。
・分母:1拍に相当する音符の種類(4なら4分音符、8なら8分音符)
・分子:1小節内に入る音符の数
例えば、4/4拍子は「1小節内に4分音符が4つ」のリズムです。
ダンスミュージックのバスドラが「ズン、ズン、ズン、ズン」と鳴る「4つ打ち」を耳にしたことがあると思いますが、これがまさに4/4拍子です。
一方、3/4拍子は「1小節内に4分音符が3つ」のリズムです。
ワルツなどでよく聴く「ズンタッタ」のリズムですね。
では、2/4拍子や6/8拍子はどうでしょう?
2/4拍子は「1小節内に4分音符が2つ」、いわゆる行進曲のリズムです。
軽快で前進していくような感覚がありますね。

そして6/8拍子は「1小節内に8分音符が6つ」のリズムです。
この拍子の種類の中で、「3/4拍子と6/8拍子、何が違うの?」とよく聞かれますが、
実はアクセントの位置が違うんですね。
2小節のパターンで考えると以下のようになります。
『』が強、「」が中、カッコなしが弱です。
・3/4拍子:|『1』、2、3|『1』、2、3|
・6/8拍子:|『1』、2、3、「4」、5、6|『1』、2、3、「4」、5、6|
3/4拍子は「ズンタッタ~、ズンタッタ~」というリズムです。
6/8拍子は「タタタ、ツタタ」のようなリズムで、
アクセントが「1拍目」と「4拍目」に付き、2拍子のような揺れを感じさせます。
アクセントを意識すると、拍子の違いを感じ取りやすくなりますよ(^-^)
音楽ジャンルごとの、良く使われる拍子
拍子によって、音楽の雰囲気や、使われるジャンルも変わってきます。
以下は代表的な例です。
・4/4拍子:ポップス、ロック、ダンスミュージックなど。
特にポップスやロックでは最も一般的な拍子です。
「ズン、ズン、ズン、ズン」という「4つ打ち」はダンスミュージックによく使われますね。
・3/4拍子:ワルツ、クラシック、童謡など。
優雅で牧歌的なイメージです。
・2/4拍子:マーチ、行進曲、ポルカなど。
行進にぴったりのリズムです。
・6/8拍子:バラード、ブルース、ケルト音楽など。
「タタタ、タタタ」のリズムが心地よい揺れを生み出します。
他にも、7/8拍子や5/4拍子など、複雑な拍子もあります。
これらは「不規則で複雑な感覚」を与えるので、プログレッシブロックやフュージョンでよく使われます。
また、曲の途中で拍子を変えるテクニックも使われます。
拍子の選び方と、拍子の感覚をつかむ練習法
拍子を選ぶ際には、曲の雰囲気や感情に合わせて決めると良いでしょう。
例えば、穏やかで優雅な曲を作りたい場合は3/4拍子を選び、
軽快さや揺れを感じさせたい場合は6/8拍子を選ぶと良いですね。
一方、ノリの良いポップスやロックなら4/4拍子を選びます。
拍子の感覚をつかむには、まずはDTMで「拍子の設定」をしたうえで、
以下のように打ち込んで練習してみると良いでしょう。
・4/4拍子
これはもっともよく使われる拍子なので、特に練習の必要はないと思いますが、
キックを1拍目と3拍目、スネアを2拍目と4拍目に配置してみると感覚がつかみやすいと思います。
・3/4拍子
キックを1拍目、スネアを2拍目と3拍目に配置します。
「ズンタッタ~」のリズムを感じてみましょう。
・6/8拍子
キックを1拍目、スネアを4拍目に配置し、ハイハットで「タタタ」のリズムを追加すると、分かりやすいと思います。
7/8拍子や5/4拍子など複雑な拍子も、まずはDTMで拍子の設定をしたうえで
キックやスネアを打ち込んで、感覚をつかんでみてください。
拍子が設定されているループ素材を聞いてみるのも、良い練習になると思います。
DTMソフトの中にも、いろいろ入っていると思います。
4/4拍子や3/4拍子に慣れてきたら、
6/8拍子や複雑な拍子にもぜひ挑戦してみてください。
最初は戸惑うかもしれませんが、
感覚がつかめるようになると、表現の幅がぐんと広がりますよ。
🎵ちなみに、拍子など深い部分を意識して作曲をしていると
「もっと打ち込みや録音の質を上げたい」「そろそろ楽器や機材を見直したい」と感じるかもしれません。
「もっといい音で録りたいな」「そろそろ機材を入れ替えたいな」と思うこと、ありませんか?
古くなった楽器や、今使っていない楽器や機材を手放せば、
「あなたの才能をもっと引き出せる新しい楽器」を購入する資金に変えられるかもしれません。
せっかくなら高く買取ってくれる業者を選んで、あなたの音楽創作活動をワンランクアップさせましょう!
🎵プロの作曲コーチが厳選!楽器別おすすめ買取業者紹介シリーズ
🎸【ギター】
▶︎ ギターの買取おすすめ業者25選&あなたに最適な業者の見極め方
🎹【電子ピアノ・キーボード・シンセサイザー】
▶︎ 買取おすすめ業者30社比較!口コミや注意点も
🎹【アコースティックピアノ】
▶︎ 失敗しない買取業者おすすめ14社とピアノを売る注意点、買取相場や口コミも
🥁【電子ドラム】
▶︎ 買取おすすめ業者10選!出張対応や相場、価格比較など
まとめ|拍子の違いが分かれば、作曲の幅が広がる!
拍子の種類が分かると、音楽を「聴く」だけでなく「作る」視点でも楽しめるようになります。
どんなリズムが曲に合うか、どう展開させていくか。
拍子をコントロールできるようになると、作曲の自由度が大きく広がります。
まずは4/4拍子・3/4拍子・6/8拍子の違いをしっかり理解して、
あなたの音楽に新しい表現を取り入れてみてくださいね(^◇^)ノ
→音楽制作の知識大全「音楽レシピ(作り方)の図書館」のもくじへ戻る