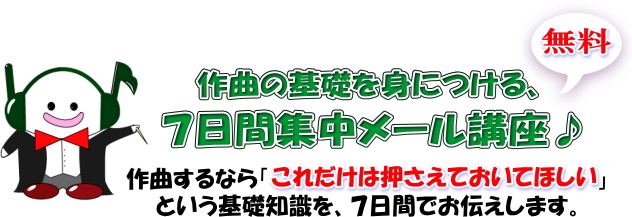■わくわく作曲先生HOME > DTM、作曲、レコーディングの豆知識 > ミキシング時などに気をつけたい、低音の性質ミキシング時などに気をつけたい、低音の性質難易度3★★★☆☆___________ 今回は「低音の性質」について書いてみましょう。 通常、スピーカーが2つあると、 左右から聞こえるように配置しますよね。 これに、ウーファーと呼ばれる、低音担当のスピーカーがある場合、 ウーファーは、真ん中に置くと思われるかもしれません。 ですが、ウーファーを置く位置は、 真ん中でなくても良いのです。 これは、「低音は拡散する性質がある」ためです。 そのため、真ん中に置かなくても、 低音を「感じられる」のです。 「大編成のオーケストラ」のコントラバスも、 客席から向かって右側に配置されていますが、 真ん中寄りから聞こえます(客席の位置にもよりますが)。 これも、低音が拡散している事が理由です。 それに加えて、コントラバスには、 面白い仕組みがあります。 コントラバスの下側から、棒が伸びているのを 見たことがあるでしょうか? コントラバスは大きいので、その大きさを支えるという意味もありますが、 この棒が実は、ステージの床に「低音の振動」を伝え、 ステージ全体が、ウーファーの役目を果たしている場合もあります。 ミキシングをする際、パン(楽器の位置)を設定しますが、 以上の性質から、ベースやコントラバスなどの低音楽器は、 真ん中にしておくと、バランスが良い場合が多いです。 左右どちらかに片寄らせるよりも、 真ん中にしておいた方が、拡散している感じが伝わりやすいですからね。 ただ、小編成のオーケストラや、 アンプラグド(スピーカーを使わず、生楽器のみの音を伝える演奏)のジャズなどの場合、 コントラバスは右側に配置し、 実際の楽器の位置を再現するのも良いでしょう。
 →わくわく作曲先生「作曲87の法則」へ戻る | |||
|
よくある質問|作曲ノウハウ|コミュニティ Waimプロデュース 4th-signal MusicのTOPページ 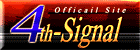 Copyright(C) 2003-2014 4th-signal Music All rights reserved このサイト内の音楽、画像、文章の無断使用はご遠慮下さい。 |