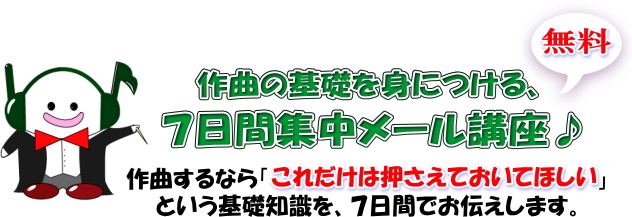■わくわく作曲先生HOME > DTM、作曲、レコーディングの豆知識 > ベロシティの基本と応用ベロシティの基本と応用難易度3★★★☆☆___________ 今回は「ベロシティ」について、少し詳しく書いてみましょう。 ベロシティとは、DTMに「音データ」を入力する際の、 楽器を弾いたり、吹いたり、たたいたりする「強さ」を表す数値です。 「音量」と混同しやすいので 気をつけましょう。 「音量」を上下させても、音質は変わりませんが、 「ベロシティ」を上下させると、音量と共に音質も変わりますからね。 たとえば、ドラムの「スネア」を やさしくたたいた音と、 激しくたたいた音では、 音量だけでなく、音質が変わります。 ギターの弦をかるくはじいた音と、 思いっきり強くはじいた音も、 音量だけでなく、音質が変わりますよね。 リアルな音を再現している音源は、 ベロシティによって、音質が変わるように設定されています。 このように、「ベロシティによる音質変化」も意識して 打ち込むようにすると良いですよ。 なお、サンプリング音源は、実際の楽器音を録音し、 その音を再現する仕組みですが、 良い音色になればなるほど、 ベロシティごとの割り当てが細かくなります。 たとえば、楽器を3段階の強さで弾き、 弱く弾いたものを「ベロシティ弱の時に鳴る音」、 適度な強さで弾いたものを「ベロシティ中の時に鳴る音」、 強く弾いたものを「ベロシティ強の時に鳴る音」、 のように設定します。 これだと、1音に対して、 3つのサンプリング音を割り当てた状態ですよね。 一方、楽器を12段階の強さで弾き、 最も弱く弾いたものを「ベロシティ1〜10の時に鳴る音」、 次に弱く弾いたものを「ベロシティ11〜20の時に鳴る音」、 ・ ・ ・ 最も強く弾いたものを「ベロシティ110以上の時に鳴る音」、 のように設定します。 これだと、1音に対して、 12のサンプリング音を割り当てた状態なので、 よりリアルな音を再現できます。 良い音源は、その分、 データ容量が大きくなるということですね。 応用としては、ベロシティを基準に、 別々の音色を割り当てることもできます。 たとえば、「ベロシティ100以下の時だけ鳴る設定」にした音色と、 「ベロシティ101以上の時だけ鳴る設定」にした音色を組みあわせ、 1つの音色を作ります。 このようにすれば、1つの鍵盤を弾いたとしても、 ベロシティ100以下の時はストリングス音色、 101以上の時はティンパニの音色、のような設定も可能です。 このような設定にしておくと、 ライヴでキーボードを弾く時に、 音色切り替えが一瞬で行えます。 以上のように、ベロシティを意識すると、 シンセの理解も深まりますよ。
 →わくわく作曲先生「作曲87の法則」へ戻る | |||
|
よくある質問|作曲ノウハウ|コミュニティ Waimプロデュース 4th-signal MusicのTOPページ 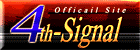 Copyright(C) 2003-2014 4th-signal Music All rights reserved このサイト内の音楽、画像、文章の無断使用はご遠慮下さい。 |