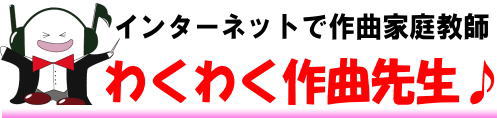| 作曲講座内容(もくじ) |
【作曲講座紹介】 |卒業生が選ぶ、わくわく作曲先生の特徴TOP7| |全カリキュラム紹介|コースと料金| 【各編の内容】 |初級編|中級編|上級編|DTMアレンジ編|DAWミキシング編 |シンセサイザー総合実践編| ジャンル別_王道作曲編| |AI作詞作曲編|フォローアップ| |
AI(人工知能)作詞作曲編♪
(※AIを使った作詞作曲に興味があれば受講)
最近のAIの発展スピードはすさまじいですね!
一昔前までは、芸術分野にAIは入って来ないと言われていましたが、
芸術分野まで入って来ました。
音楽も例外ではありません。
作曲家や作詞家にとってAIは脅威ですが、AIを理解することで、
逆に、味方にすることも出来ます。
味方にすれば、これほど心強い味方はいません♪
このAI作詞作曲編では、まずは自力で作詞できる作詞技術を習得していただき、
そのあとで、AIを使った作詞、作曲を紹介します。
- 作詞の基礎技術
- あなたの個性を活かしつつ、AIを使って短時間で作詞する方法
- あなたの個性を活かしつつ、AIを使って短時間で作曲する方法
- 作詞作曲だけでなく、アレンジやミキシングなどにも使えるAIツールの紹介
AI作詞作曲編のカリキュラム(全4回)
わくわく作曲先生のAI作詞作曲編で紹介する作詞方法は、
一般的に公開されているAI作詞方法とは異なり【超実践的】です。
僕のオリジナルなので、おそらくネットや本で探しても見つからないと思います(^-^)
(ひょっとしたら、僕が見つけられていないだけかもしれませんが)
ただ、この方法を使うためには、
最低限の作詞の知識が必要です。
作詞の基本が身についていないと、AIに正しい指示を送れないし、
返ってきた回答の良し悪しも判断できないからです。
そのため、まずはAIを使わなくても、
自力で作詞できるようになっていただきます。
【第1回の内容】
- そもそも作詞とは何か?
- 作詞をするときに意識しておくべき大切なコツ
- 作詞を始める前に決めておく3つのこと
- 作詞の手順
- 文章が思い浮かばないときの、おすすめの方法
- 歌詞の世界を広げるための、3つのテクニック
- 2コーラス目以降の歌詞はどうする?
- メロディに歌詞をあてはめるときに重視すること
- 比喩表現、擬人法、倒置法、体言止め、英語表記などのテクニック
- 歌詞が出来上がって、最終確認の方法
など
ここでは、ChatGPTというAIを使って作詞する方法を習得していただきます。
※ChatGPTのコツが理解できるので、作詞以外にもChatGPTを応用できるようになります。
先ほど、AI作詞作曲編で紹介する作詞方法は、
超実践的なオリジナルの方法と書きました。
一般的なAI作詞方法との大きな違いは
AI作詞作曲編は「曲先」「個性を活かせる」という2点です。
一般的なAI作詞は、詞先が多いですが、
世の中の曲は、9割以上が曲先です。
・詞先=先に歌詞を作り、そのあとで歌詞にメロディを付ける作り方
・曲先=先にメロディを作り、そのあとでメロディに歌詞を乗せる作り方
そのため、AI作詞作曲編では「曲先」での作詞で進めます。
また、ChatGPTに歌詞を作ってもらうというスタンスではなく、
ChatGPTチームのリーダーをあなたが勤め、
チームとして歌詞を作りあげるような作り方をします。
そのため、あなたの個性を活かした歌詞になります。
【第2回の内容】
- AIを使った作詞と、自力での作詞の違い
- ChatGptの準備と注意点
- AIを使った作詞の手順
- プロンプトとは?
- 正確な回答を得るための、前提プロンプト
- 登場人物を考えるためのプロンプト
- あらすじを考えるためのプロンプト
- サビの歌詞を考えるためのプロンプト
- Bメロの歌詞を考えるためのプロンプト
- Aメロの歌詞を考えるためのプロンプト
- 思った回答が得られないときのプロンプト
など
音楽系AIには、いろんな種類があります。
大きく分けると、以下のように分類できます。
・作詞系(ChatGptなどの文章作成ツールを活用)
・作曲系
・アレンジ系
・ミキシング、マスタリング系
・その他(ボーカル加工や波形分離など)
この第3回では、作曲系のAIを2種類紹介します。
1つは最新のAI「SUNO AI」です。
ほとんどの生徒さんは、このAIのクオリティに驚愕します!
下手をすると、作曲の意欲を失ってしまいそうなくらいです(^^;
ただ、編集しづらい、著作権的に問題アリという欠点があります。
ですが、AI作曲の現在地を知るには最適です。
もう1つ「AIVA」は、クオリティはまだそれほどではありませんが、
編集がしやすいAIです。
AIとの付き合い方を学ぶには、こちらのAIのほうが適しているので、
こちらを主に紹介します。
このAIで、AIとの付き合い方を学んでおけば、
今後、もっと進化したAIが出てきても、活用していけるようになるでしょう。
【第3回の内容】
- 音楽系AIの種類
- Suno AIの紹介と使い方
- AIVAの紹介と使い方
第4回は、第3回の続きです。
(DAWソフトによって変わるので、生徒さんのDAWに合わせて講座内容をカスタマイズします)
まずはAIVAを使って、実際に曲を作ってもらいながら、
AIとの付き合い方を習得してもらいます。
内容的には、第2回で紹介した作詞方法を
作曲編曲にも応用するような内容になっています。
その後は「ミキシング、マスタリング系」のAIを紹介します。
ミキシング、マスタリング系はほとんどが有料なので、
今回は紹介だけにとどめています。
次に、ステム分離という、
CDやmp3の楽曲を、パート別に分離させるAIを紹介し、
実際に使っていただきます。
たとえば、曲の中からボーカルだけ抜き出して、ボーカルとカラオケに分ける。
ドラムだけ取り出す。ベースだけ取り出す。
さらにそれをDAWに取り込んで編集する。ということができます。
ステム分離ができる、無料で使えるツールも紹介します。
(高度なことをするには有料)
最後に、ボーカル系AIを紹介します。
ただ、ボーカロイドは有名すぎて、AI作詞作曲編で紹介しなくても情報はあふれているので、
ボーカロイドは省略させていただきますm(__)m
その他のボーカル系AIを紹介だけします(今回は、使い方は省略させていただきます)。
【第4回の内容】
- AIVAを使った作曲とアレンジ
- DAWでさらに編集し、仕上げる方法
- ミキシング、マスタリング系AIの紹介
- ステム分離のAIツール紹介と使い方
- ボーカル系AIの紹介